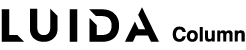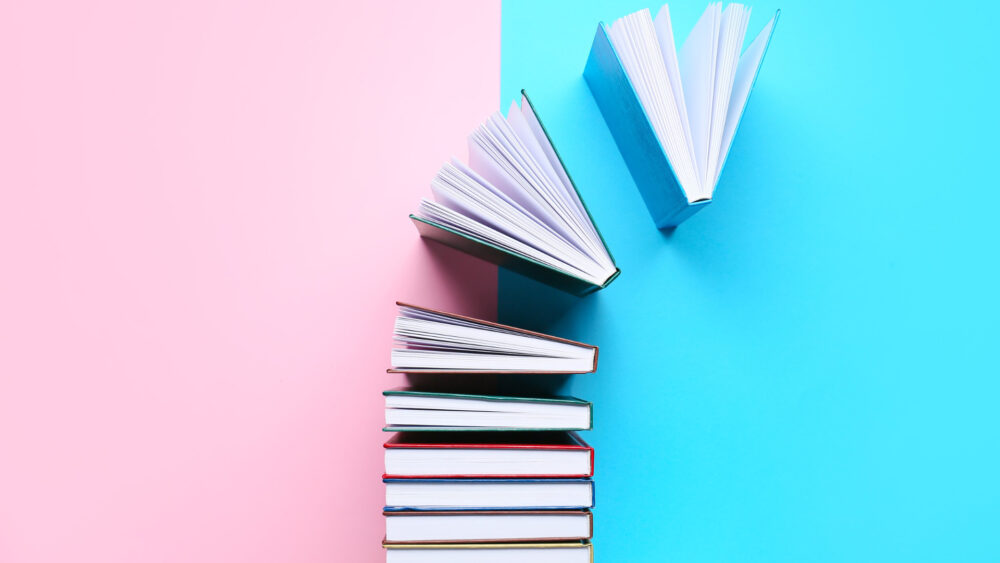「LInuxってプログラミングで必須って言うけど、何から勉強したらいいの?」
関連する内容がとても多いLinux、勉強を始めてみたけど、一体何から手をつけたらいいのかわからないですよね。
LInuxにはさまざまな本があり、それを使うことで興味ある分野の勉強を効率的に進められます。
そこで、今回は「Linuxを学ぶために読むべき本10選」を紹介していきます。

役に立ちそうな本を見つけてみましょう!
Linux習得で本を読む3つのメリット
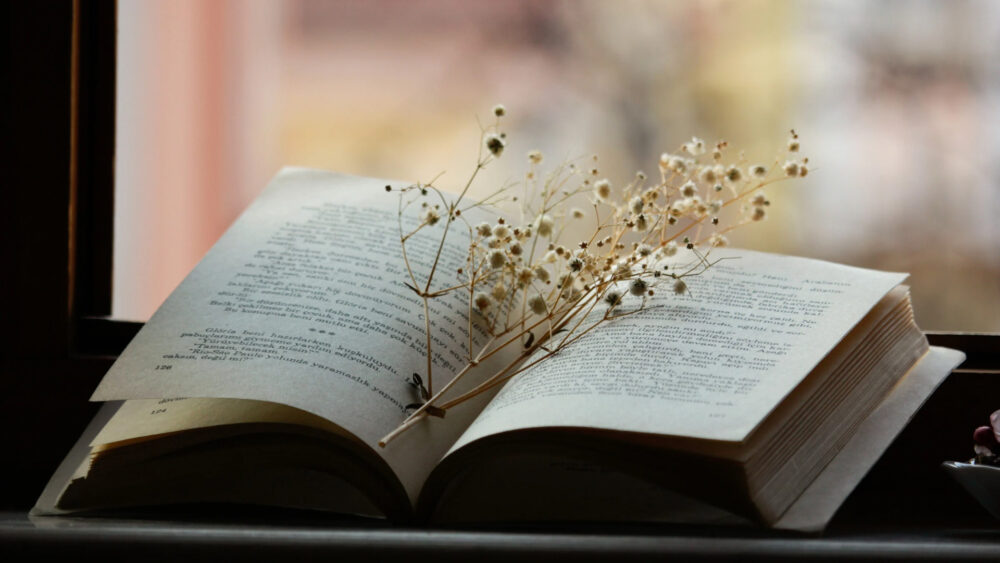
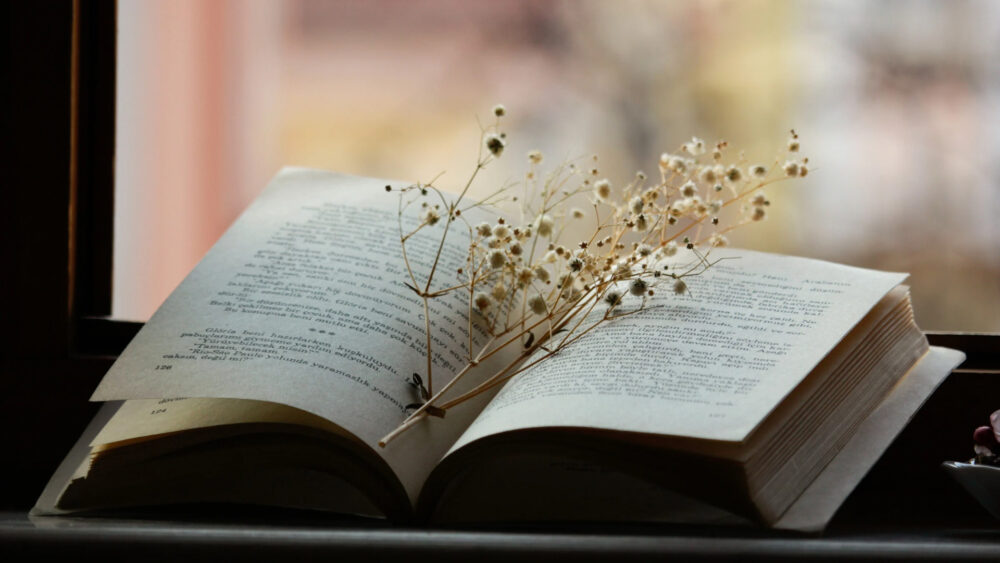
Linuxはインターネットを調べてもたくさんの情報が出てきます。インターネットと比べた本で勉強するメリットは以下の3つです。
Linuxを本で勉強するメリット
- 体系立てて知識を学べる
- 実践的なスキルの向上
- 情報の信頼度が高い



インターネットで学ぶのとは別のメリットがあります!
それぞれを解説していきますね。
メリット①体系立てて知識を学べる
本で勉強する一番のメリットは体系立てて知識を学べることです。
Linuxの本には、分野別に情報が整理して記述されており、基礎から応用まで、さまざまな分野を網羅的かつ段階的に学習できます。これによって、興味のある分野にスムーズにアクセスして、計画的に学習できます。
また、初心者向けにわかりやすくまとめられています。確かに、公式ドキュメントの信頼性は高く、積極的に読むべきですが、専門用語が多く初心者には敷居の高い一面もあります。まずは本で内容を大まかに理解して、公式ドキュメントの記載内容の理解を深めるといった組み合わせをすると、スムーズにインプットできます。
メリット②実践的なスキルの向上
コマンドを組み合わせたり、LInuxを使ってサーバーを作ったりといった実践的なスキルの向上の観点でも、本を使った学習は有用です。
まず、本には具体的な例が多数掲載されており、それらを使ってみることでスキル向上に直結します。手法だけでなく、その手法を使う理由まで掲載されているため、LInuxに関する理解を深めることも可能です。
また、本にはさまざまな一問一答形式の問題が掲載されており、それらに向かい合うのも大事です。問題を解いてみることで、コマンド作成・問題解決能力を大幅に上げられます。
実践的スキルの向上は、単に本を読むだけでは不十分です。知識を実際のプロジェクトや作業に適用し、継続的に学習と実践を繰り返すことが重要です。本から学んだテクニックやノウハウを実際に使用し、実践することで、初めて「Linuxが使える」と言えるでしょう。
メリット③情報の信頼度が高い
プログラミング教本で、最も重要なのが情報の信頼度です。媒体によっては著者の理解が間違っており、誤った知識を記述している場合があります。その場合事実と異なる理解をしてしまうことになりかねません。
本は、信頼性の観点から他の多くのリソースよりも優れています。本に記載された情報は、一般的に出版前に厳密な校正やレビューを受けます。これにより情報の正確性や信頼性が確保されます。
一方で、インターネット上の情報、特に個人ブログやSNSは注意が必要です。誰でも編集や投稿ができるため、間違った情報や偏った見解が含まれる可能性があります。
Linuxの本の選び方
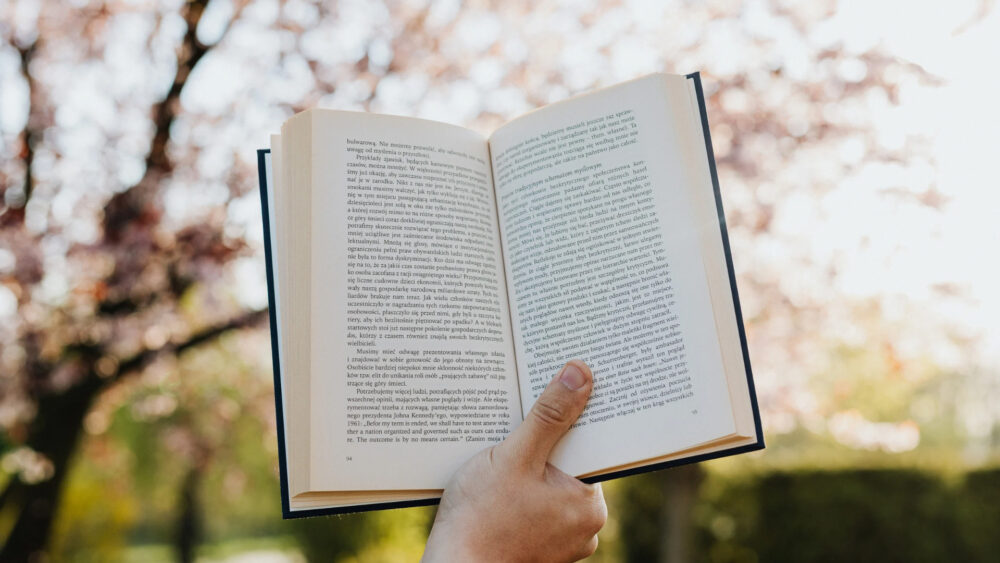
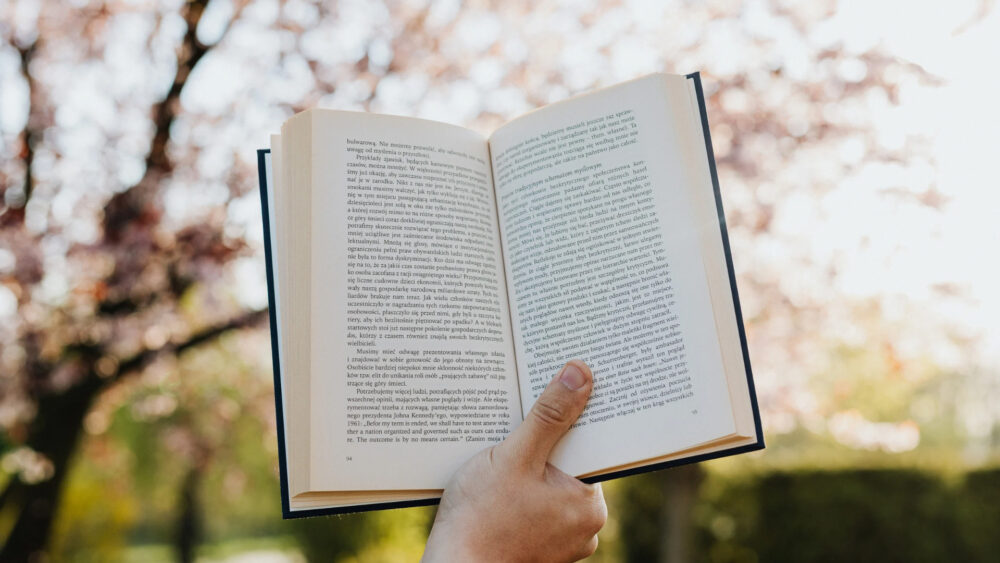
勉強する際は可能な限り質の高い本を手に入れたいですよね。Linuxの勉強において良質な本を選ぶ際は以下の3点に注意するとよいでしょう。
本を選ぶ際に見るべきポイント
- 内容の難易度
- 内容のバランスと詳しさ
- 情報の新しさ



どこを見るべきか解説します!
内容の難易度
適切なLinuxの学習本を選ぶためには、難易度の確認が重要です。本のレベルは、初級、中級、上級と様々ですので、自分の現在の知識やスキルに最も適した本を選ぶ必要があります。本のレベルと自身のレベルが合致していないと、本の内容が理解できない、簡単すぎて意味がないなど、無駄な時間を過ごしてしまいます。
初級者は、Linuxの基本的な概念やコマンド、サーバーの活用や環境構築の方法を学びます。ただ理論が書いてあるだけでなく、実際に手を動かして学べる内容だとなお良いでしょう。
本のレベルを知るためには目次を確認し、その内容が自分の学習目標やニーズに適しているか検討しましょう。また、Webサイトのレビューなども有用です。これにより、適切な本を選ぶことができ、効果的な学習が期待できます。
内容のバランスと詳しさ
適切なLinux学習本を選定する際、内容のバランスと詳しさの確認は必須です。
バランスの良い本は、基礎知識から応用まで、さまざまな分野の幅広くカバーし、読者が全体的な知識を均等に得られるよう構成されています。また内容が詳しく書かれている本は、特定の分野について一冊だけで知見を深められます。
良いバランスと適切な詳しさを持つ本は、Linuxの多様な側面と特性を総合的に学習するのに適しています。基本コマンド、システム管理、ネットワーク設定、セキュリティーなど、多岐にわたる知識が整理され、一冊の本で学べるよう配慮されているのが理想です。それぞれのトピックが適切に深掘りされていると、理論と実践の両方で洞察を得ることができます。
適切な内容のバランスと深度を持つ本を選ぶことで、Linuxの知識を系統的かつ効果的に身につけ、より深い理解と実践的なスキルの向上が期待できます。
情報の新しさ
Linuxの学習資料を選ぶ際、情報の新しさの確認は不可欠です。Linuxだけでなく技術はは絶えず進化しており、時代遅れとなり得ます。最新かつ正確な知識を習得するためには、出版日やバージョンをチェックし、最新の情報が含まれているか確認する必要があります。
例えば、OSのバージョン確認はとても重要です。Ubuntuなどの最新バージョンを確認し、できるだけ近いバージョンが紹介されている本を選びましょう。
一方、LInuxでは、長い年月を経っても変わらない内容もあります。Linixコマンドなどはその一例で、こういった分野では長期間辞書のように使える一冊を手元においておくと良いでしょう。
Linuxのオススメの本10選
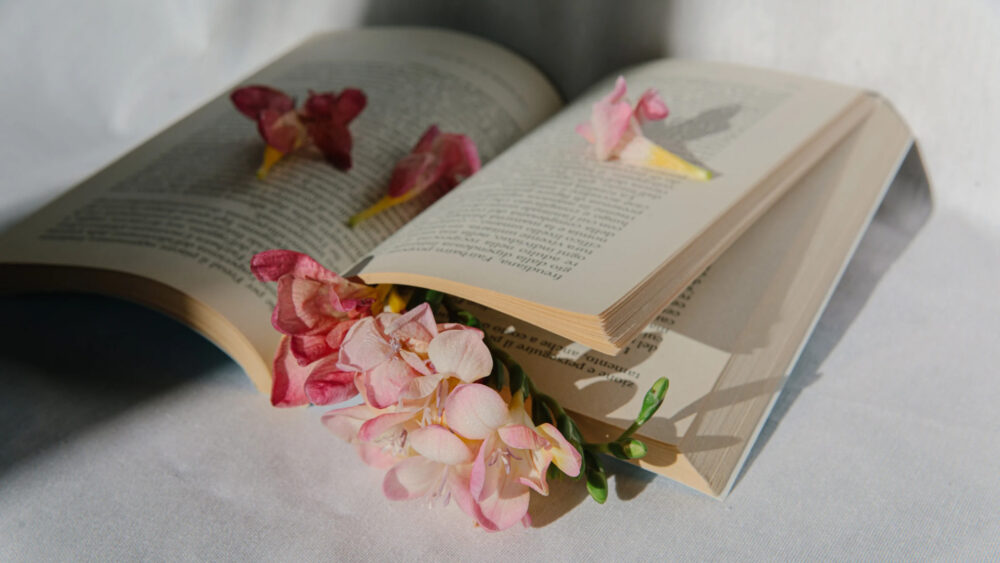
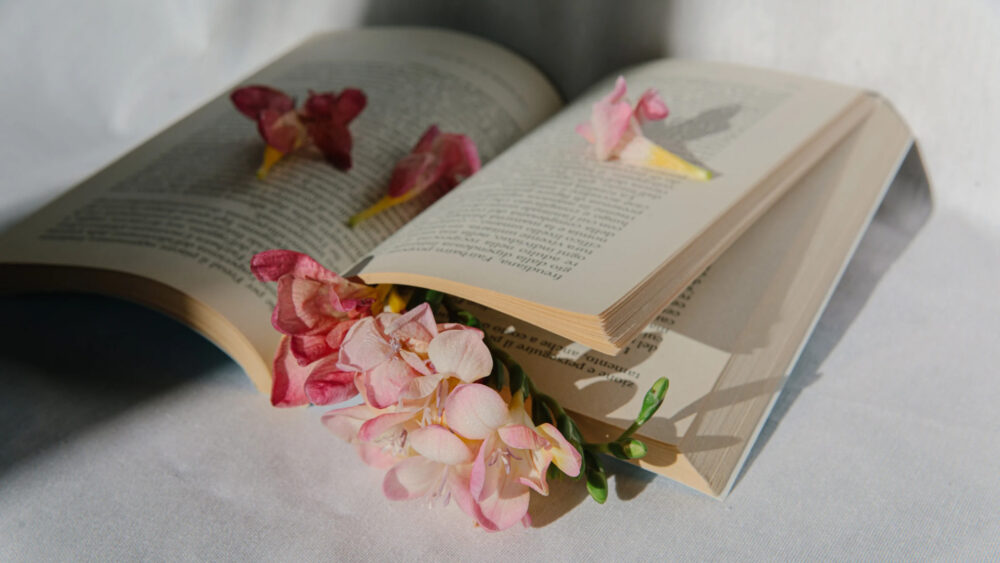
実際にどのような本を選べばいいのでしょうか。
この記事ではおすすめの本を10冊まとめたので、それぞれを紹介いたします。さまざまな難易度や内容の本があるので自分に合ったものを探してみたり、複数購入したりするのもいいでしょう。
LInuxのおすすめの本10選
- エンジニア1年生のための世界一わかりやすいLinuxコマンドの教科書
- 新しいLinuxの教科書
- ITエンジニア1年生のための まんがでわかるLinux コマンド&シェルスクリプト基礎編
- 本気で学ぶ Linux実践入門 サーバ運用のための業務レベル管理術
- ゼロからわかるLinuxサーバー超入門 Ubuntu対応版
- ゼロからわかる Linuxコマンド200本ノック―基礎知識と頻出コマンドを無理なく記憶に焼きつけよう!
- Linuxのはじめ方2022-2023
- ふつうのLinuxプログラミング 第2版 Linuxの仕組みから学べるgccプログラミングの王道
- Linux教科書 図解でパッとわかる LPIC/LinuC
- Ubuntuサーバー徹底入門



自分にあった本を選んでみましょう!
①エンジニア1年生のための世界一わかりやすいLinuxコマンドの教科書
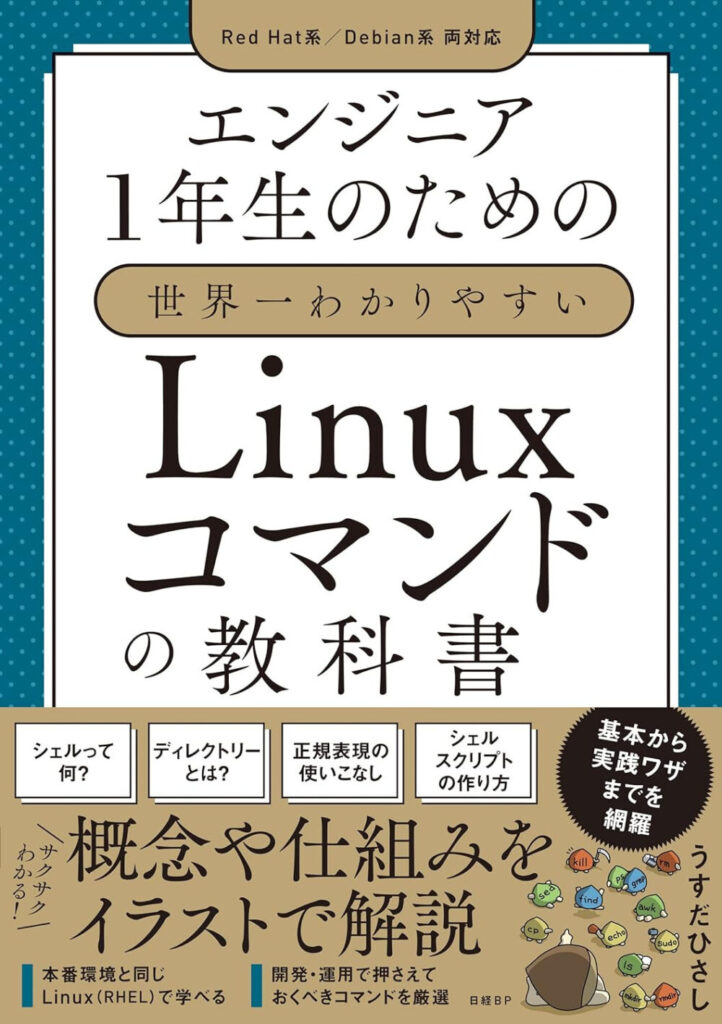
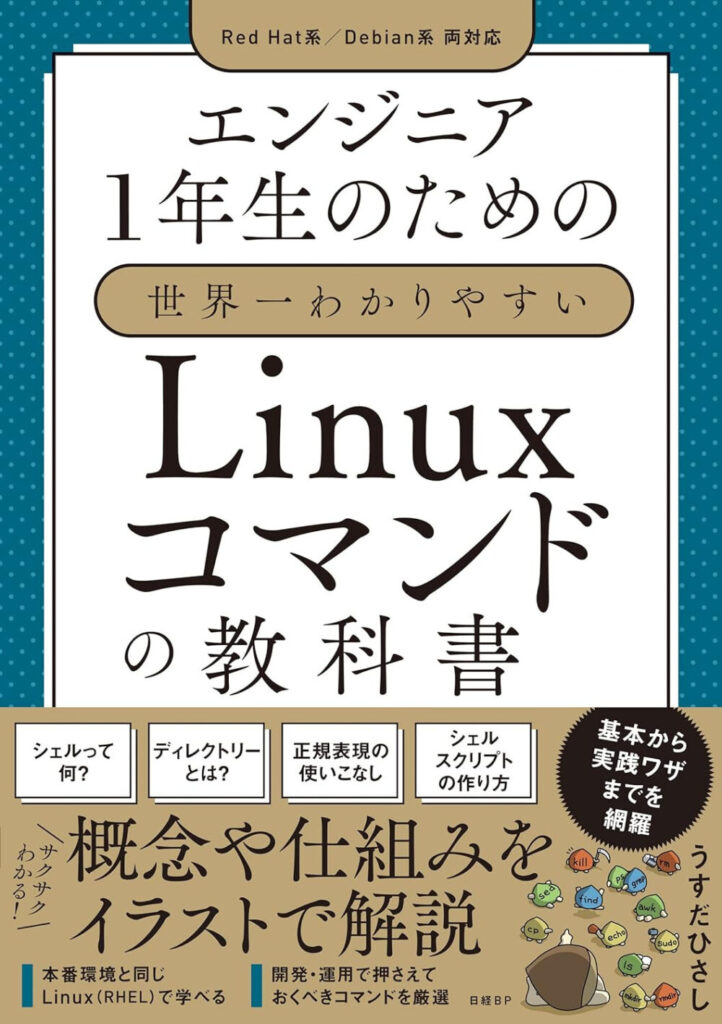
Linuxの初心者が、最初に読むのにおすすめの一冊です。Linuxコマンドを全く使ったことがないという方でも理解しやすいように、イラスト付きで解説しているのが特徴です。
LInuxサーバー管理者がよく使うコマンドをまとめているなど、実務寄りの情報も掲載されています。まずはこの本の内容を理解してからLinuxエンジニアとして現場で働いてみるとよいでしょう。
目次
第1章 Linuxの環境を作ろう
第2章 コマンドラインとシェルの関係を理解しよう
第3章 Linuxの構造を頭の中に叩き込もう
第4章 コマンドの実行結果を活用しよう
第5章 コマンドの実行を制御する仕組みを知ろう
第6章 テキストファイルをエディタで編集。加工しよう
第7章 ファイルをコマンドで編集・加工しよう
第8章 指定した文字を含むファイルを高精度に見つけよう
第9章 コマンドラインを効率よく使いやすくしよう
第10章 スーパーユーザーの役割を知っておこう
第11章 シェルスクリプトを作って一括で処理しょう
第12章 Linuxサーバー管理者なら押さえておくべきネットワークの必須コマンド
②新しいLinuxの教科書
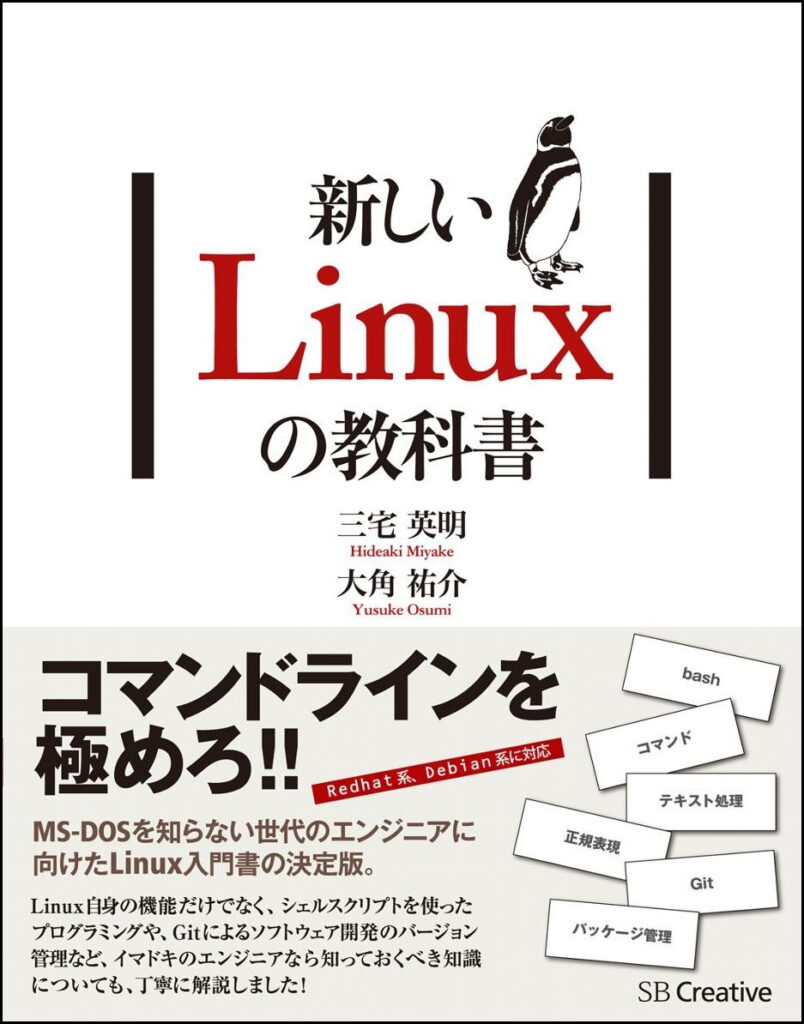
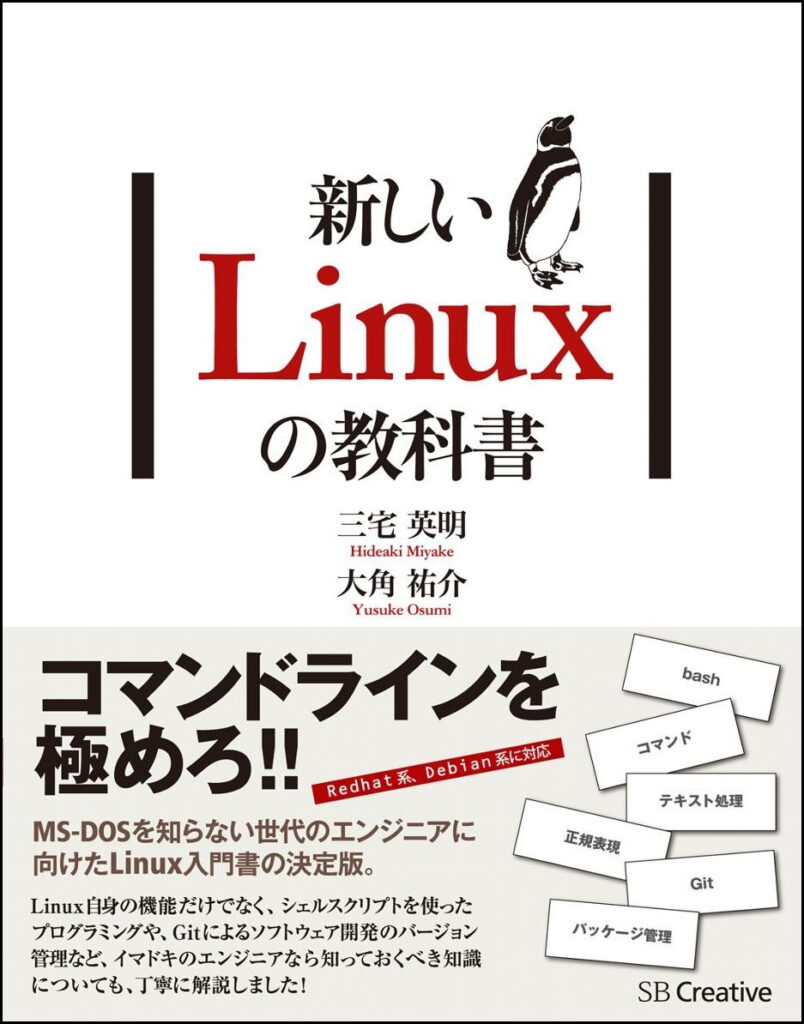
こちらもLInux入門書ですが、正規表現や標準入出力、ソフトウェア開発のバージョン管理など、より多彩な内容が掲載されています。
Linux以外にも、Gitを使ったバージョン管理など、開発に役立つような知識も掲載されているので、幅広い知識を取り入れたい方におすすめです。
目次
CHAPTER01 Linuxを使ってみよう
CHAPTER02 シェルって何だろう?
CHAPTER03 シェルの便利な機能
CHAPTER04 ファイルとディレクトリ
CHAPTER05 ファイル操作の基本
CHAPTER06 探す、調べる
CHAPTER07 テキストエディタ
CHAPTER08 bashの設定
CHAPTER09 ファイルパーミッションとスーパーユーザ
CHAPTER10 プロセスとジョブ
CHAPTER11 標準入出力とパイプライン
CHAPTER12 テキスト処理
CHAPTER13 正規表現
CHAPTER14 高度なテキスト処理
CHAPTER15 シェルスクリプトを書こう
CHAPTER16 シェルスクリプトの基礎知識
CHAPTER17 シェルスクリプトを活用しよう
CHAPTER18 アーカイブと圧縮
CHAPTER19 バージョン管理システム
CHAPTER20 ソフトウェアパッケージ
APPENDIX 01 リモートログインとSSH
02 infoドキュメントを読む
03 Linuxと日本語入力
04 参考文献
③ITエンジニア1年生のための まんがでわかるLinux コマンド&シェルスクリプト基礎編
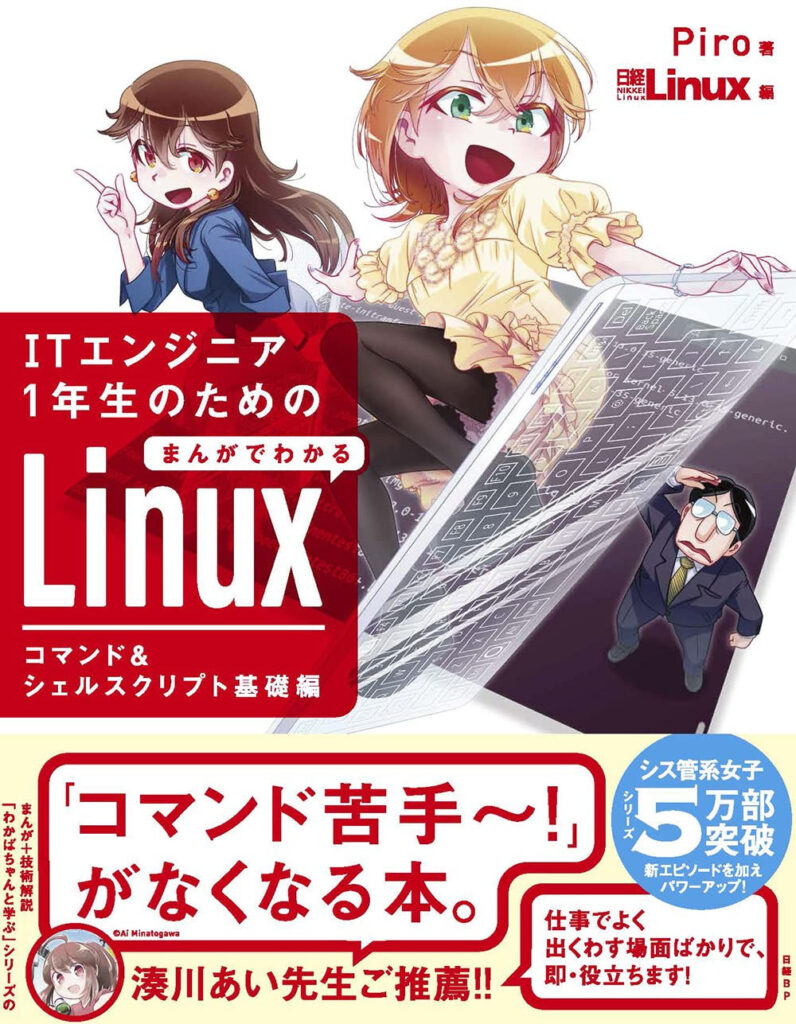
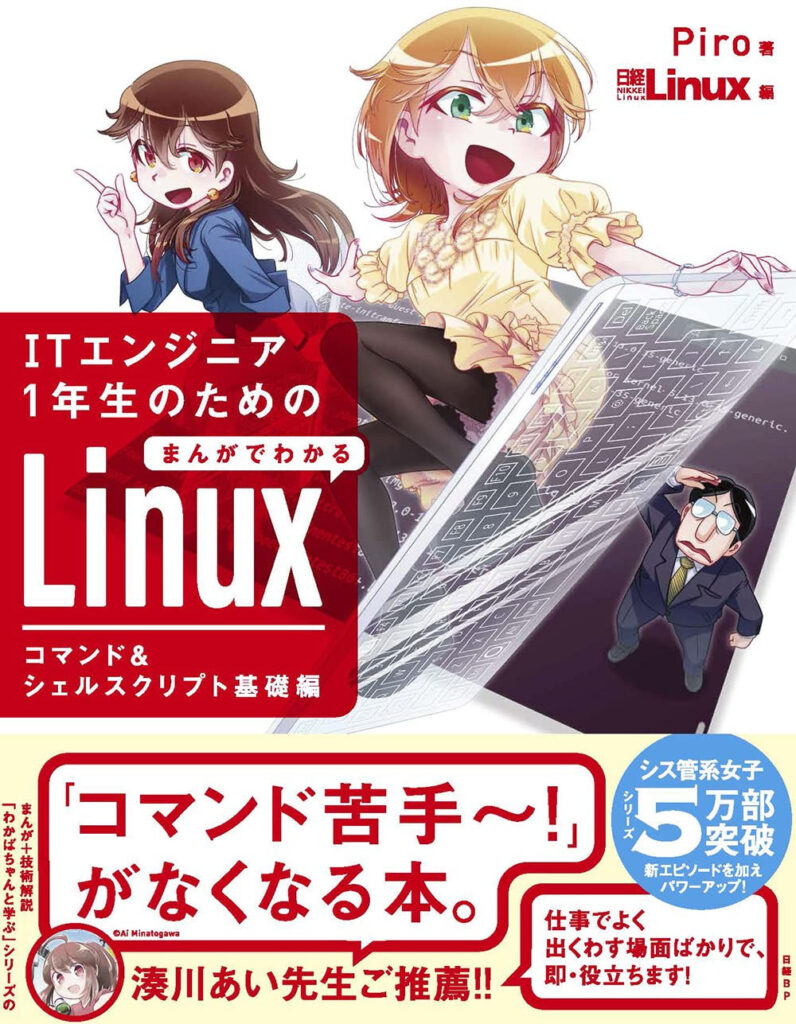
Linuxコマンドについて漫画でわかりやすく解説している一冊です。かわいいキャラクターのやり取りを見ながら進めるので、技術書についてややこしさを感じている人にはおすすめです。
一方、内容はLinuxのかなり奥深いところまで網羅しているので、初心者から上級者に至るまで長い間愛用できる一冊です。
目次
プロローグ 誕生! シス管系女子
第1話 他のコンピュータをリモートで操作したい
第2話 一時的に管理者権限で操作したい
第3話 さまざまが語句を一度で検索したい
第4話 端末でも対話的なファイルを編集したい
第5話 vimでもコピー&ペースト&アンドゥしたい
第6話 コマンド操作でファイルを移動・コピーしたい
第7話 ファイルの位置を相対パスで思い通りに指定したい
第8話 似たような名前のファイルをまとめて操作したい
第9話 「原本のファイル」と常に同じ内容になる「分身のファイル」を作りたい
第10話 突然の回線切断から復帰したい
第11話 他の操作の結果を見ながら操作したい
第12話 最近実行したコマンドを呼び出したい
第13話 ずっと前に実行したコマンドを呼び出したい
第14話 ネットワーク越しにファイルをコピーしたい
第15話 システムの過負荷を把握したい
第16話 システムのメモリー不足を把握したい
第17話 ログファイルから必要な行だけ取り出したい
第18話 作業手順を自動化したい
第19話 同じ文字列をスクリプトの中で使い回したい
第20話 環境や状況に合わせてスクリプトを動かしたい
第21話 ログファイルから必要な列だけ取り出したい
第22話 同じ内容の行を数えたい
第23話 CSV ファイルの行を列の内容で並べ替えたい
第24話 コマンドラインの指定で動作を変えたい
第25話 条件に応じて処理の流れを変えたい
第26話 コマンドの異常終了に対策したい
第27話 複数の対象に同じ処理を繰り返し実行したい
第28話 共通の処理を何度も再利用したい
第29話 定期的に行う作業を自動実行したい
第30話 鍵認証で安全にログインしたい
第31話 定時処理で自動的にscpしたい
第32話 複数のサーバーのファイルを効率よく収集したい
第33話 条件に当てはまるログの行数を集計したい
第34話 複数のテキストファイルを一括編集したい
第35話 表記が一定でない語句をまとめて置換したい
第36話 正規表現のパターン指定をもっと簡潔にしたい
第37話 正規表現のパターン指定をさらに簡潔にしたい
④本気で学ぶ Linux実践入門 サーバ運用のための業務レベル管理術
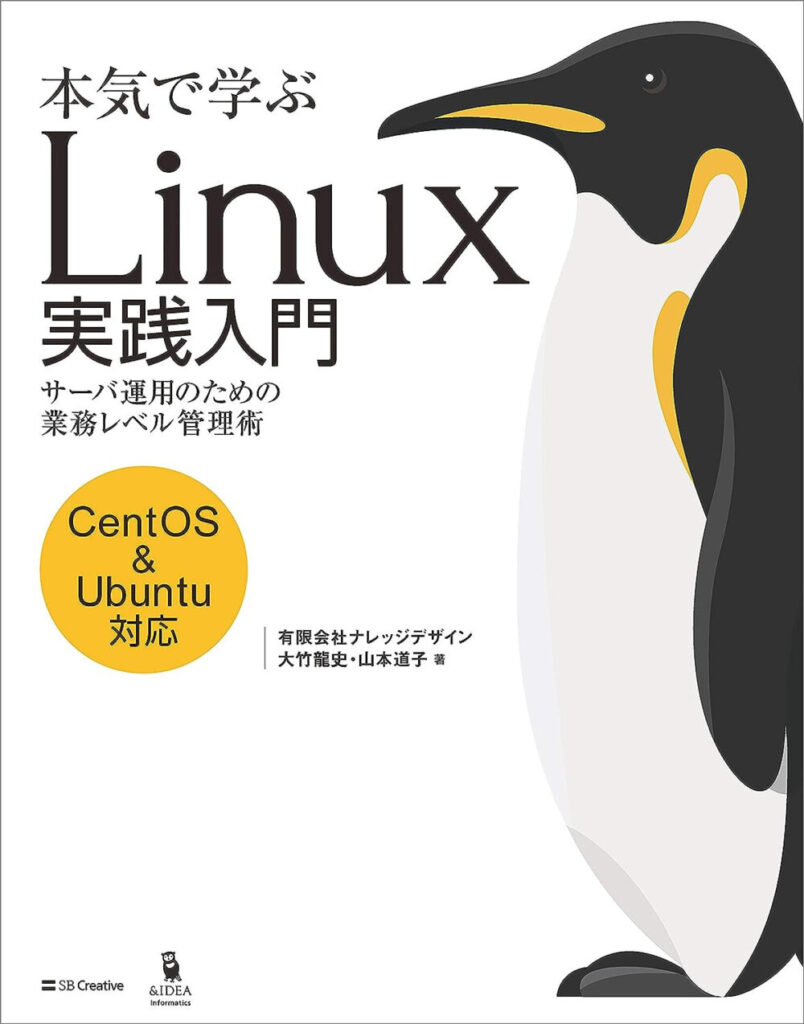
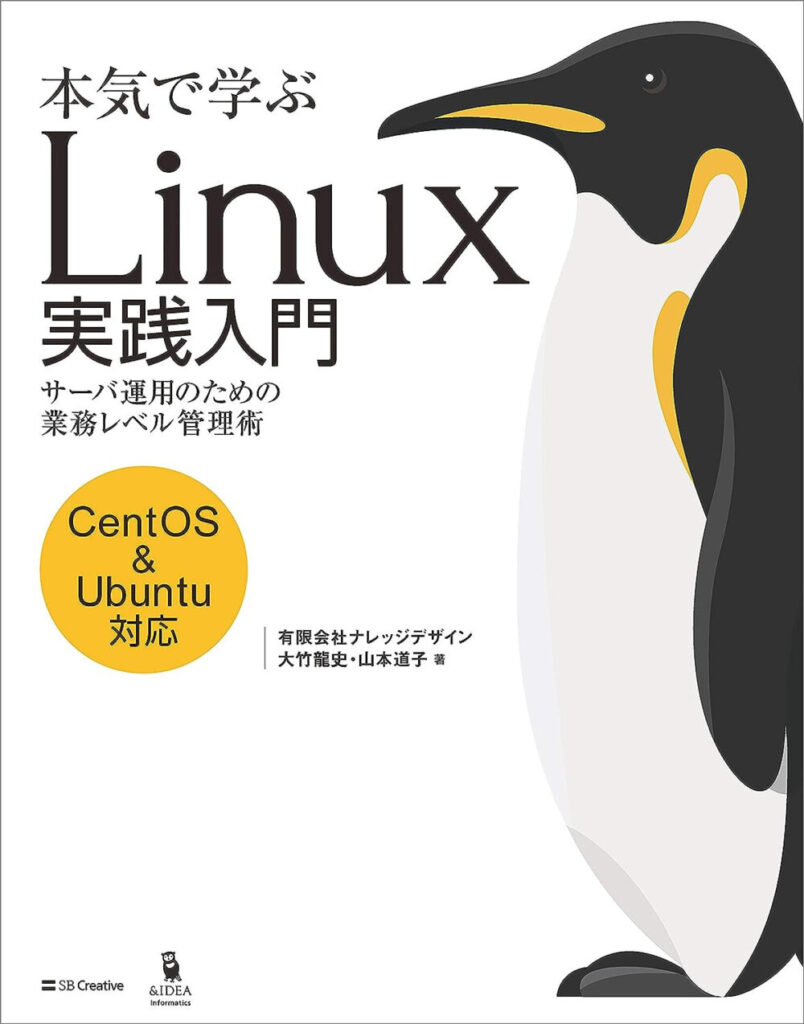
サーバー管理者が日々の管理業務に使うコマンドをまとめた一冊です。シチュエーションごとに構成されているため、必要なときに情報を探しやすいのが魅力です。
よく使われるディストリビューションであるCentOSとUbuntuの違いも網羅されており、実務でディストリビューションを使いたい人にも勧められる一冊です。(ただし、CentOSはサポート終了が発表されたので注意しましょう。)
目次
はじめに
本書の表記について
Chapter1 Linuxの概要と導入
Chapter2 Linuxの起動・停止を行う
Chapter3 ファイルを操作する
Chapter4 ユーザを管理する
Chapter5 スクリプトやタスクを実行する
Chapter6 システムとアプリケーションを管理する
Chapter7 ディスクを追加して利用する
Chapter8 ネットワークを管理する
Chapter9 システムのメンテナンス
Chapter10 セキュリティ対策
Appendix 仮想環境を構築する
⑤ゼロからわかるLinuxサーバー超入門 Ubuntu対応版
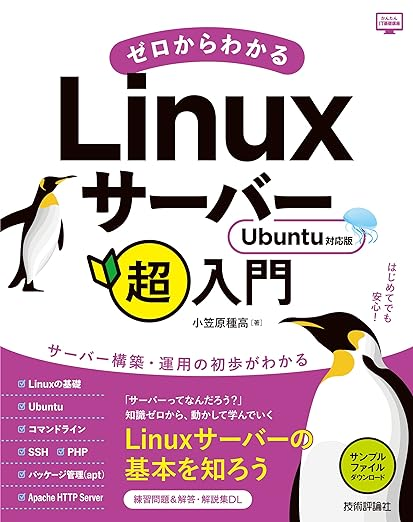
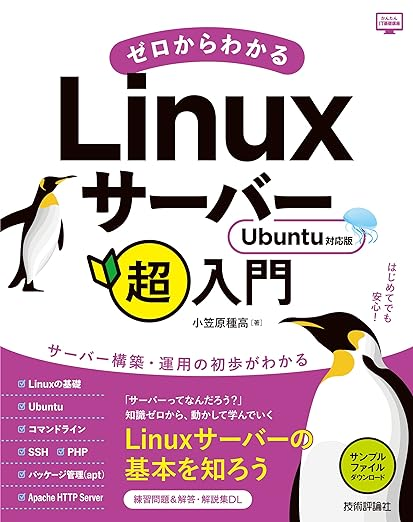
Ubuntuをベースにサーバ構築のイロハを学べる一冊です。Apache HTTP Serverの使い方やPHPを使ったサーバーサイドプログラミングも学べるため、サーバーを動かしてみたい方の入門書としてはぴったりです。
「サーバーはなにか」というところから、自分でウェブサイトを作れるようになるまでこれ一冊でカバーしています。
目次
CHAPTER 1 サーバーをはじめよう
1-1 サーバーの仕事と役割を知ろう
1-2 サーバー構築に必要なものを知ろう
1-3 サーバーOSについて知ろう
1-4 サーバーの基本を知ろう
1-5 自分のパソコンにサーバーを作ろう
CHAPTER 2 サーバーを構築しよう
2-1 サーバーをつくるための流れ
2-2 VirtualBoxをインストールしよう
2-3 Ubuntu Serverをインストールしよう
2-4 仮想マシンの停止と開始
CHAPTER 3 Ubuntuを操作しよう
3-1 サーバーの操作を身につけよう
3-2 ファイル操作を理解しよう
3-3 終了の方法を理解しよう
3-4 ユーザーとグループを理解しよう
3-5 ソフトウェアのインストールと更新
CHAPTER 4 Webサーバーを利用しよう
4-1 サーバーとソフトウェア
4-2 Webサーバーを立てる
4-3 Apacheをインストールする
4-4 Apacheを起動しよう
4-5 IPアドレスを確認しよう
4-6 ブラウザから接続してみよう
CHAPTER 5 リモートから操作できるようにしよう
5-1 SSHでリモートから操作する
5-2 サーバー側のSSHの準備
5-3 クライアント側のSSHの準備
5-4 SSHで接続する
5-5 コンテンツを配置する
5-6 Tera TermやWinSCPでファイル転送する
5-7 ファイアウォールの設定を確認する
5-8 SSHのポートを変更する
CHAPTER 6 Webサーバーの設定を変更しよう
6-1 Apacheの設定ファイルを編集する
6-2 エラーページをカスタマイズしてみよう
6-3 Webサイトへのアクセスを制限する
CHAPTER 7 Webサーバーでプログラムを実行させよう
7-1 Webサーバーでプログラムを動かす
7-2 PHPの環境を整える
7-3 PHPのプログラムを作ってみよう
7-4 ページにリンクを張ったり画像を表示したりしてみよう
CHAPTER 8 Webサーバーを公開・管理しよう
8-1 Webサーバーを公開するために必要なこと
8-2 レンタルサーバーを借りてログインしよう
8-3 ログを確認しよう
8-4 サーバーは正常に動いているのか確認しよう
8-5 バックアップをとろう
8-6 セキュリティに注意しよう
8-7 サーバーに関わる仕事
⑥ゼロからわかる Linuxコマンド200本ノック―基礎知識と頻出コマンドを無理なく記憶に焼きつけよう!
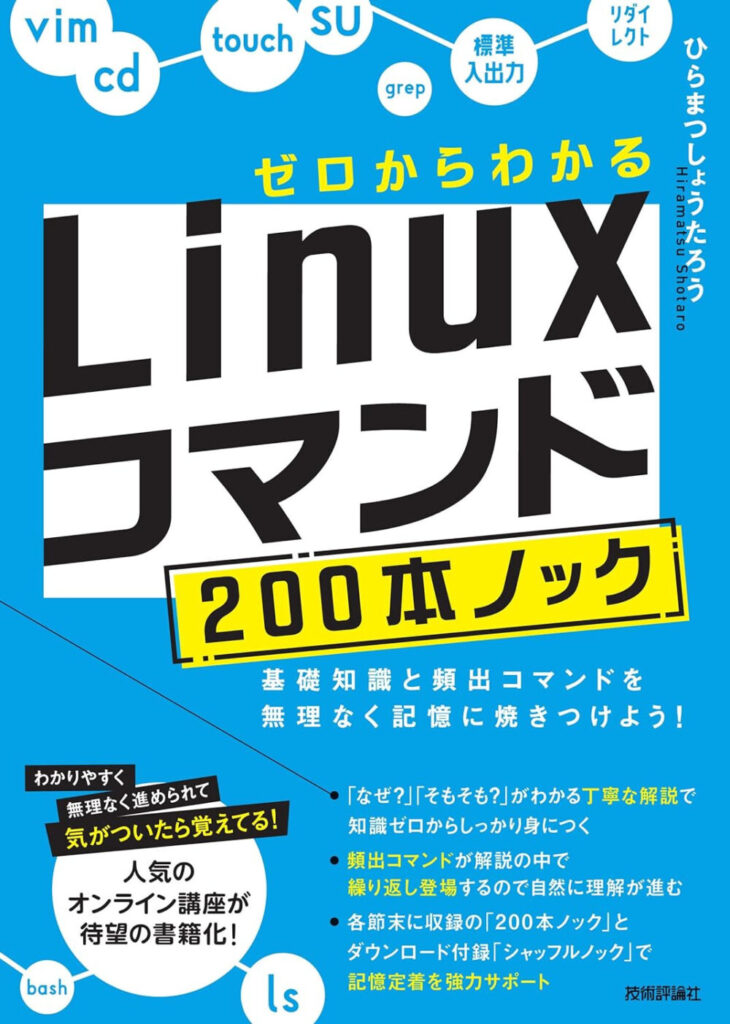
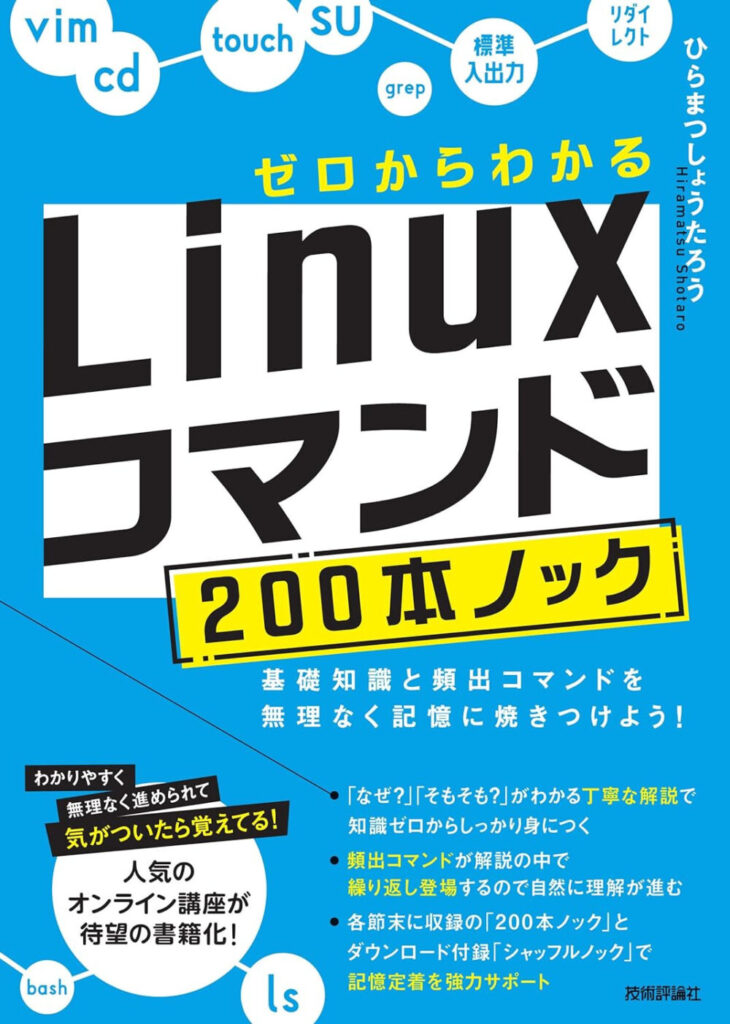
実務で頻出するLinuxコマンドを厳選してまとめた一冊です。Linuxコマンドは逐一検索していると時間が取られることが多く、一部のコマンドやその組み合わせはすぐ入力できるようにしておく必要があります。
この本はLinuxコマンドを演習で繰り返し解くため、しっかりと体に身につきます。Linuxはエンジニアなら必携の知識なので、繰り返し解いて体に染み付けましょう。
目次
第1章 Linuxの基本
1.1 Linuxとは
1.2 Linuxカーネルとは
1.3 Linuxディストリビューションとは?
1.4 Linux OSとサーバー
1.5 GUIとCLI
1.6 なぜLinuxコマンドを学ぶ必要があるのか?
1.7 物理マシンと仮想マシン
1.8 環境構築
1.9 Linuxを学びやすくする3つの観点
第2章 ファイルとディレクトリ
2.1 Linuxのディレクトリ構成
2.2 カレントディレクトリを表示する pwdコマンド
2.3 絶対パスと相対パス
2.4 ディレクトリの中身を一覧表示する lsコマンド
2.5 カレントディレクトリを変更する cdコマンド
2.6 Linuxの歴史
2.7 標準規格
第3章 シェルとコマンドラインの基本
3.1 シェルと端末
3.2 シェルの種類とログインシェル
3.3 プロンプトとコマンドライン
3.4 コマンドが実行される流れ
3.5 OSと抽象化
3.6 コマンドラインの基本操作
3.7 コマンドのオプション
3.8 l sコマンドの主なオプション lsコマンド
3.9 コマンドの調べ方 manコマンド
第4章 ファイル操作のコマンド
4.1 ディレクトリを作成する mkdirコマンド
4.2 空のファイルを作成する touchコマンド
4.3 ファイルやディレクトリを削除する rm・rmdirコマンド
4.4 ファイルの中身を(連結して)表示する catコマンド
4.5 ファイルの一部だけを表示する head・tailコマンド
4.6 スクロール表示する lessコマンド
4.7 ファイルやディレクトリをコピーする cpコマンド
4.8 ファイルやディレクトリを移動・改名する mvコマンド
4.9 楽に引数を指定する方法 チルダ展開・パス名展開・ブレース展開
4.10 「~」「*」「{ }」などの文字を展開させずに使う エスケープ
4.11 リンクを作成して別名で呼び出せるようにする lnコマンド
4.12 ファイルやディレクトリを見つけ出す findコマンド
第5章 パーミッションとスーパーユーザー
5.1 パーミッションはなぜ必要なのか?
5.2 パーミッションを表示する ls -l
5.3 パーミッションを変更する chmodコマンド
5.4 スーパーユーザーとは
5.5 スーパーユーザーに切り替える suコマンド
5.6 スーパーユーザーとしてコマンドを実行する sudoコマンド
第6章 Vimの基本
6.1 Vimとは
6.2 Vimとモード
6.3 コマンドラインモード
6.4 インサートモード
6.5 ノーマルモード
6.6 ビジュアルモード
第7章 標準入出力の活用
7.1 標準入出力(stdio)とは
7.2 リダイレクト
7.3 /dev/null
7.4 パイプライン
第8章 テキスト処理の基本コマンド
8.1 フィルタとは
8.2 入力の行数や単語数などを出力する wcコマンド
8.3 入力を並べ替えて出力する sortコマンド
8.4 入力の重複を取り除いて出力する uniqコマンド
8.5 入力の文字を置換して出力する trコマンド
8.6 入力から指定した文字列を含む行だけを出力する
8.7 入力から指定した列だけを出力する awkコマンド
第9章 プロセスとジョブ
9.1 プロセスとは psコマンド
9.2 psコマンドでよく使うオプション psコマンド
9.3 プロセスの親子関係
9.4 ジョブとは
9.5 ジョブの一覧を表示する jobsコマンド
9.6 フォアグラウンドとバックグラウンド fg・bgコマンド
9.7 プロセスとジョブの終了 killコマンド
9.8 シグナルを送信する killコマンド
第10章 Bashの設定
10.1 エイリアスを設定する aliasコマンド
10.2 コマンドの種類を確認する typeコマンド
10.3 コマンドの優先度
10.4 シェル変数
10.5 環境変数
10.6 代表的な環境変数
10.7 Bashの設定ファイル
第11章 シェルスクリプト入門
11.1 シェルスクリプトとは
11.2 シェルスクリプトを作成してみよう
11.3 シェルスクリプトを実行してみよう
⑦Linuxのはじめ方2022-2023
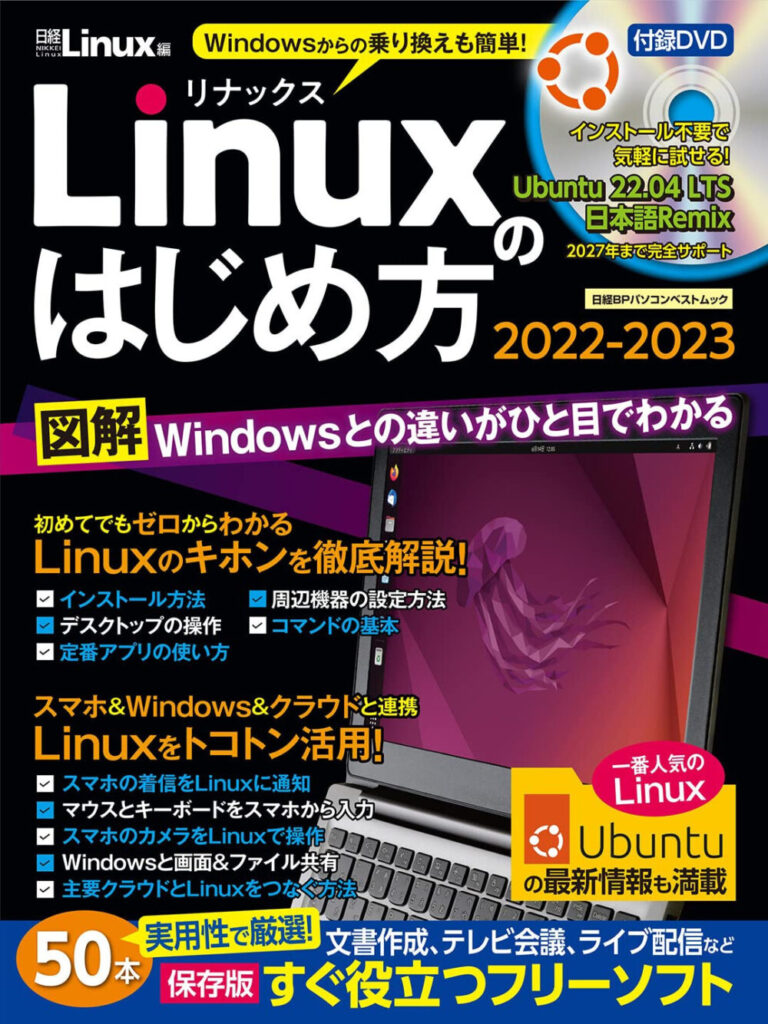
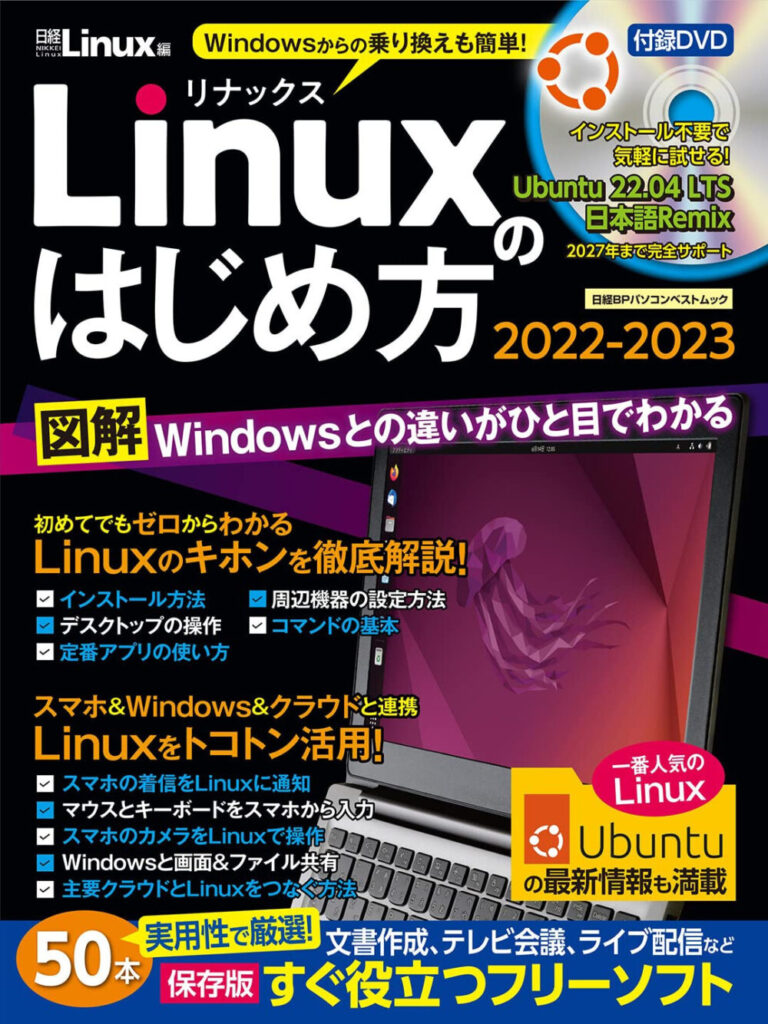
Windowsと比較しながらLinuxを解説している本です。そのためWindowsユーザーの方にはとてもわかりやすい一冊となっています。
ただLinuxコマンドを使うだけでなく、メインOSとしてLinuxやUbuntuを使う方法が解説されており、OfficeやPhotoshopに代替するフリーソフトも紹介されています。実機でメインOSとしてLInuxを使いたい人はまずはこの本から始めてみましょう。
目次
第1章 これで分かる! Ubuntuの使い方
総論 お手軽USBメモリー起動で最新Ubuntuを触り倒そう
Part1 デスクトップ編
最新LinuxならWindowsと遜色なし、デスクトップを自在に使いこなす
Part2 標準アプリ編
まずは標準アプリを使いこなす、Windowsとの違いはどの程度?
Part3 アプリの導入方法編
魅力的なアプリが選び放題、導入方法は大きく3パターン
Part4 よく使うアプリ編
OfficeやPhotoshopは使える?豊富なフリーソフトを使いこなす
Part5 設定/周辺機器編
設定の調整で使い勝手を向上、多彩な周辺機器も自在に接続
Part6 コマンド編
Linuxがもっと便利で快適に! コマンド操作の基本をマスター
第2章 実用度MAX! フリーソフト50
総論 サーバーやプログラミングまで幅広く、実用性で厳選したフリーソフト50本
デスクトップ
「Reminduck」「FileRenamer」「organize」「Vserver」「Warpinator」「Junction」「Pika Backup」「GParted」「Cairo-Dock」「Conky」「Extension Manager」「GNOME Tweaks」
文書作成
「Apostrophe」「Text Editor」「Xournal/Xournal++」「FreePlane」「Graphviz」
インターネット
「Chromium」「Newsboat」「Zoom」「Teams」「Slack」「Bitwarden」
マルチメディア
「amsynth」「GIMP」「ImageMagick」「Shotcut」「Kdenlive」「Blender」「OBS Studio」
開発&データ分析
「Visual Studio Code」「Anaconda」「JupyterHub」「bat/batcat」「exa」「fd/fdfind」「jump」
サーバー
「Hexo」「Motion」「ReadyMedia」「x11vnc」「TightVNC」「noVNC」「Dnsmasq」「Keycloak」「FreeIPA」「mkcert」「Cockpit」「Prometheus」「Docker」
コラム コマンドの使い方を表示する「man」コマンド
第3章 最新版「Ubuntu 22.04 LTS」完全解説
Part1 「Ubuntu 22.04 LTS」がリリース! 、最新技術を採用して5年間使える
Part2 見て分かる! 最新版デスクトップの使い方
Part3 最新版「GNOME 42」を採用! 最新デスクトップのカスタマイズ術
Part4 標準のディスプレイサーバーが変更! 「Wayland」の特徴と使用上の注意
Part5 旧版からの移行時に注意すべきUbuntu 22.04 LTSの変更点
Part6 ユニバーサルパッケージ「Snap」をUbuntuで使う
Part7 公式フレーバーもLTS版をリリース! 旧版からのアップグレードに注意
第4章 PC&スマホ&クラウド連携 虎の巻
Part1 スマホ連携
ファイル共有に遠隔操作も、有線/無線でスマホをつなぐ
Part2 PC連携
画面もメディアもファイルも共有、PC同士の連携方法をマスター
Part3 クラウド連携
Linuxでもクラウドを楽しむ、ストレージやメモを連携
⑧ふつうのLinuxプログラミング 第2版 Linuxの仕組みから学べるgccプログラミングの王道
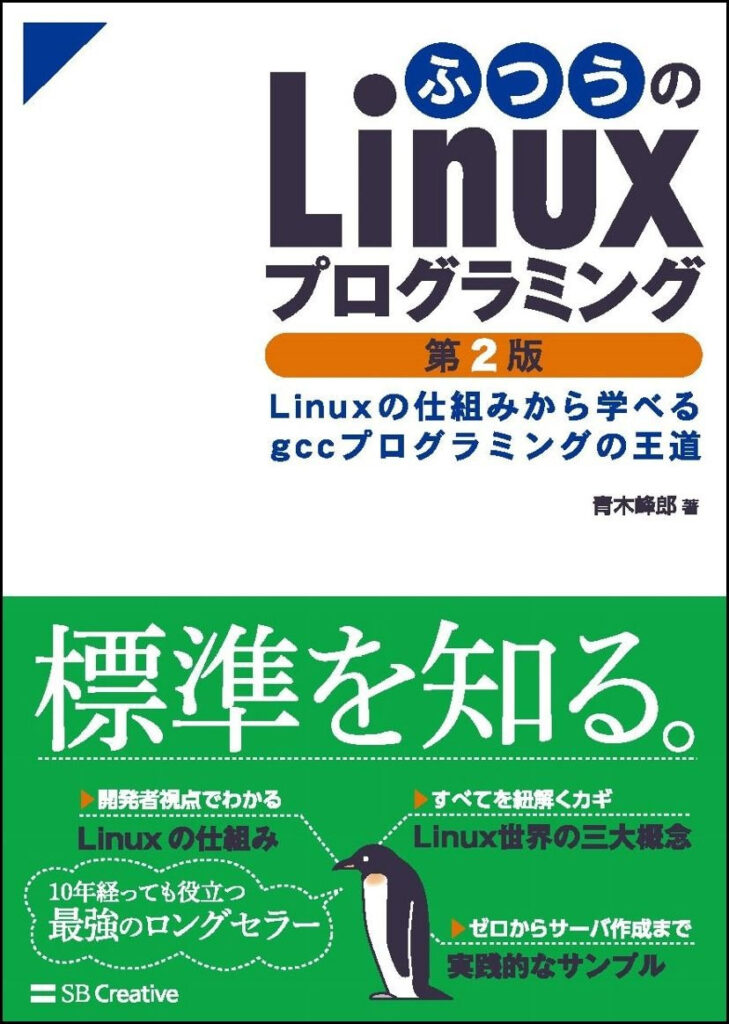
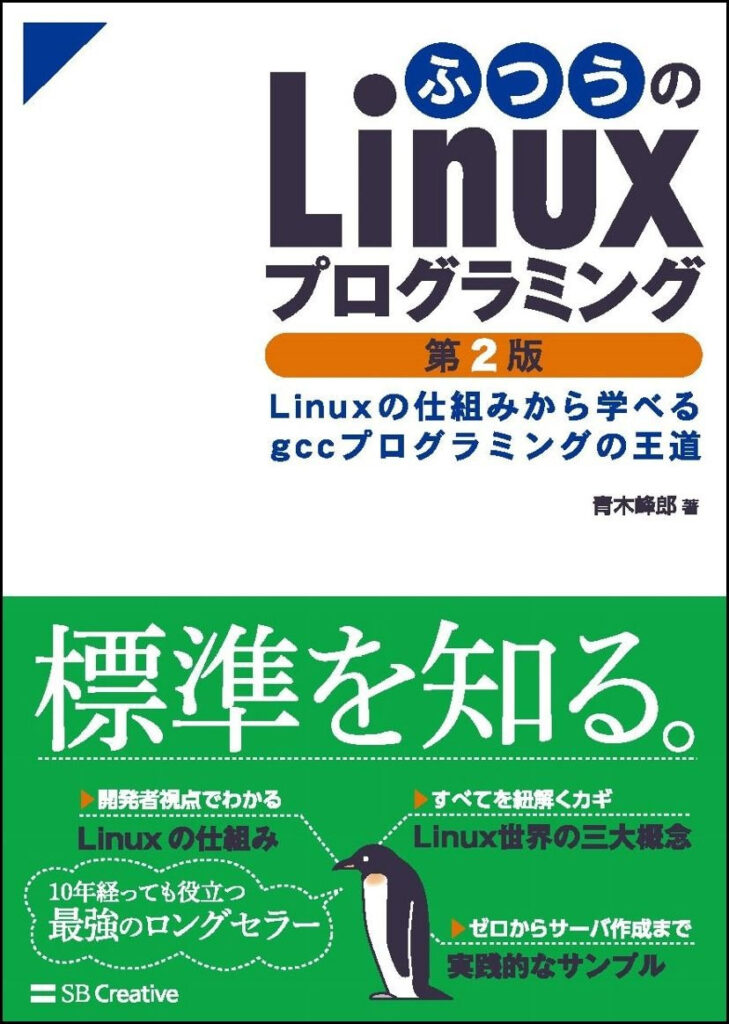
Linuxでのgccプログラミングの基礎をまとめた一冊です。「gcc」はC言語のコンパイラですが、あまりC言語については深掘りすぎず、C言語に詳しくない人でもLinuxを使ったコンパイルやHTTPサーバーの制作を学べます。
最初は文章メインで「ファイルシステム」や「プロセス」などの基礎を学びつつ、徐々に実践的なコーディングを学んでいく形式で、知識と技術を両方身につけられます。
目次
第1部 Linuxの仕組み
第1章 Linuxプログラミングを始めよう
第2章 Linuxカーネルの世界
第3章 Linuxを描き出す3つの概念
第4章 Linuxとユーザ
第2部 Linuxプログラミングの根幹
第5章 ストリームにかかわるシステムコール
第6章 ストリームにかかわるライブラリ関数
第7章 headコマンドを作る
第8章 grepコマンドを作る
第9章 Linuxのディレクトリ構造
第10章 ファイルシステムにかかわるAPI
第11章 プロセスとハードウェア
第12章 プロセスにかかわるAPI
第13章 シグナルにかかわるAPI
第14章 プロセスの環境
第3部 Linuxネットワークプログラミング
第15章 ネットワークプログラミングの基礎
第16章 HTTPサーバを作る
第17章 HTTPサーバを本格化する
第18章 本書を読み終えたあとは
付録
A.1 gccの主要コマンドラインオプション
A.2 参考文献
⑨Linux教科書 図解でパッとわかる LPIC/LinuC
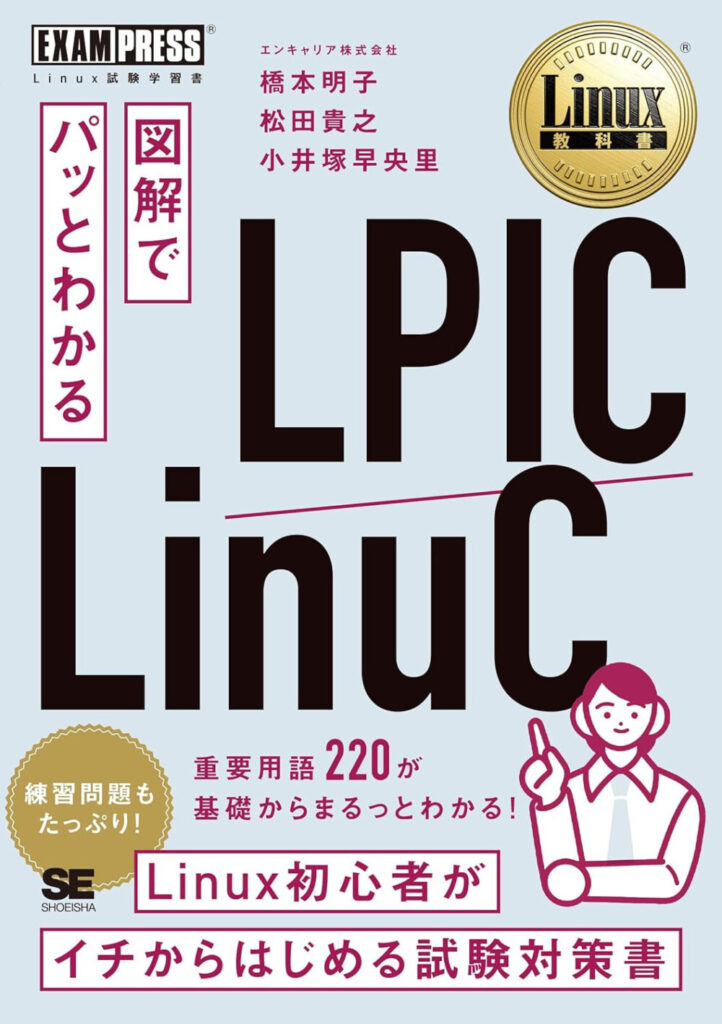
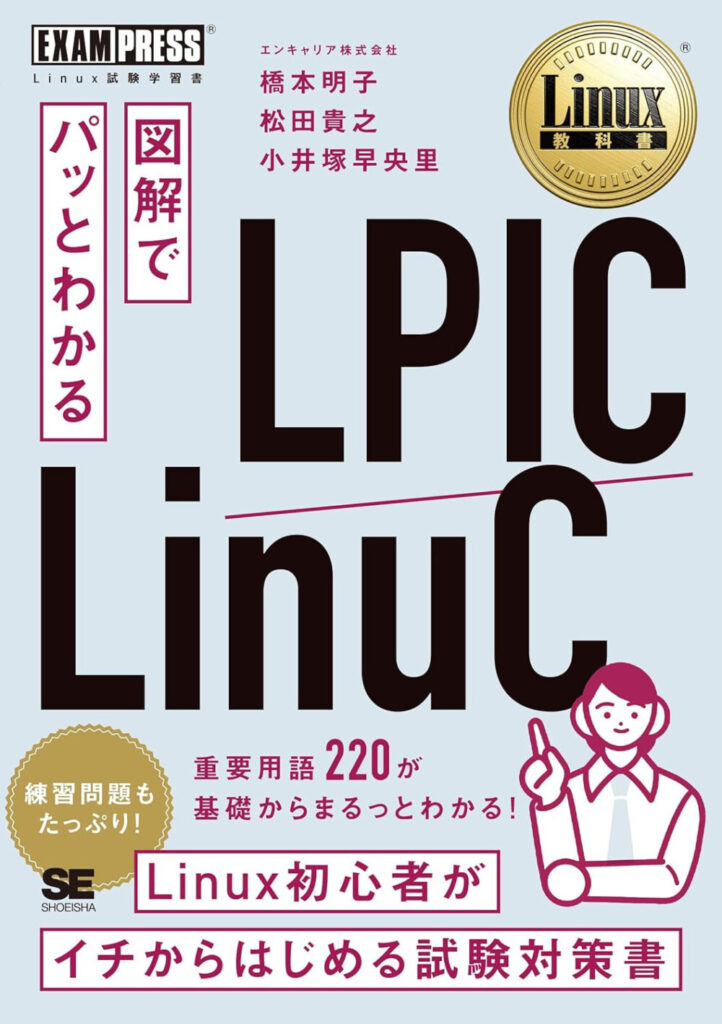
Linuxの資格・LPICとLinuCの対策のための参考書です。Linuxの基礎を一から解説しており、LPICとLinuCの過去問を通して習得できます。
Linuxを知らない人でも基礎から学び直せるので、これから学び始める方にもおすすめです。付録には「環境設定」の手引きを掲載されているため、Linuxを使ったことがない方でも安心して使えます。
目次
第1章 Linuxとは
第2章 コンピュータの基本
ハードウエア/ソフトウエア/ネットワーク/セキュリティ
第3章 Linuxの基本
基本動作/ファイル操作/テキストデータ処理
第4章 Linuxを管理する
ユーザ管理/プロセス管理/時刻管理/ログ管理/パッケージ管理/デバイス管理/ディスク管理/起動管理/ネットワーク管理/セキュリティ管理/その他管理
総合問題
⑩Ubuntuサーバー徹底入門
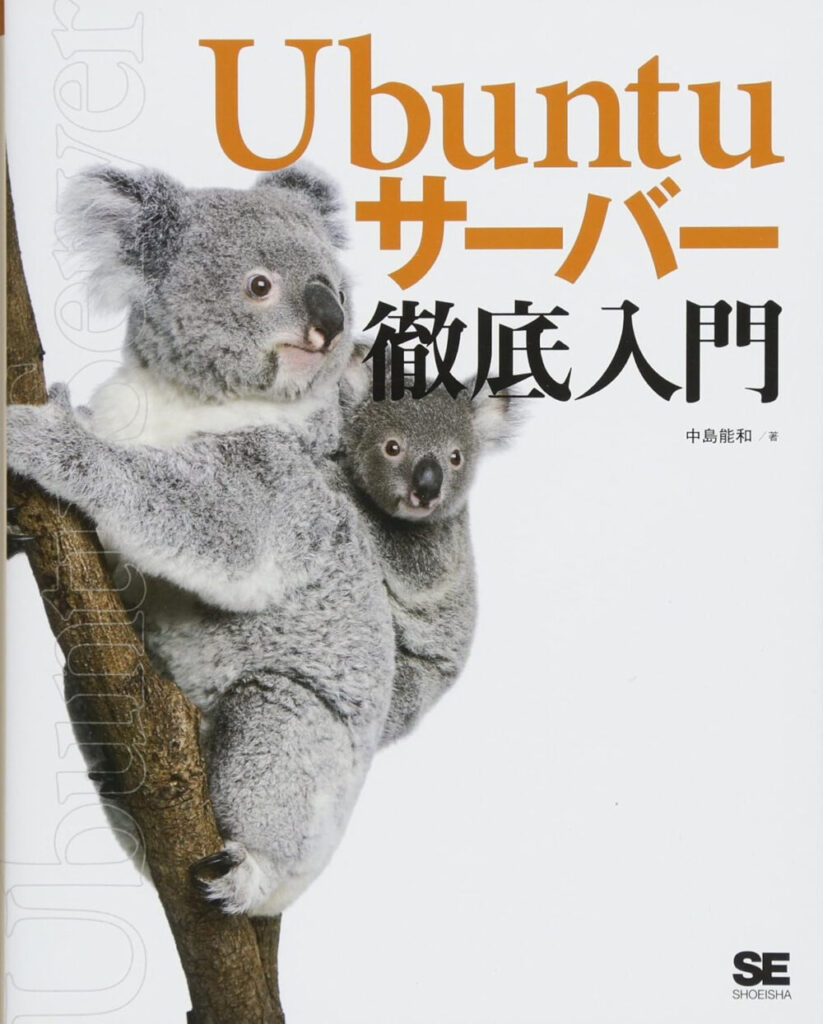
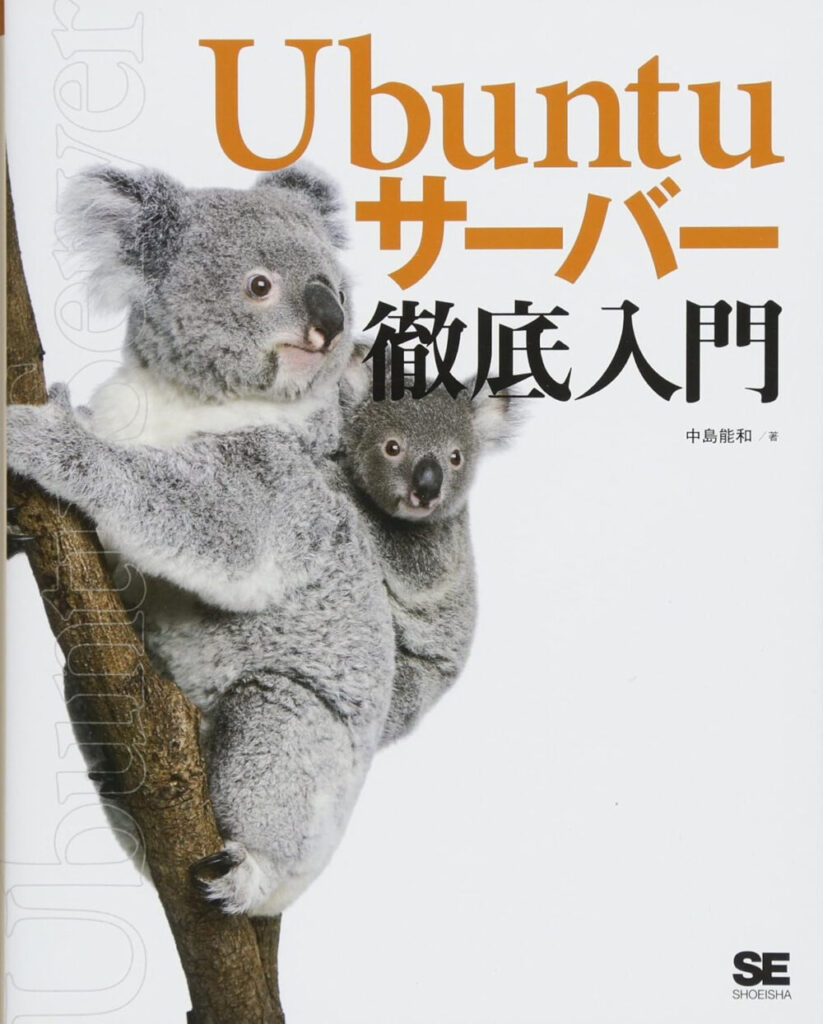
Ubuntuを使ったサーバー構築を学べる参考書です。サーバーのインストールから、パッケージの管理・代表的なアプリケーションの設定まで徹底的に学習できます。
サーバーの構築として、Webサーバー、メールサーバー、DNSサーバー、Sambaサーバー、SSHサーバー、OpenLDAPサーバー、プロキシサーバー、データベースサーバーを詳細に紹介しており、サーバー構築で躓いた際に、この本があれば安心です。
目次
第1章 Ubuntuの概要とインストール
第2章 ユーザーの基本操作
第3章 ファイル管理
第4章 ファイルシステムの管理
第5章 ネットワークの設定と管理
第6章 システムの設定と管理(1)
第7章 システムの設定と管理(2)
第8章 パッケージ管理
第9章 ログの管理
第10章 セキュリティ
第11章 Webサーバー(Apache、Nginx)
第12章 メールサーバー(Postfix)
第13章 DNSサーバー(BIND)
第14章 Sambaサーバー
第15章 SSHサーバー
第16章 OpenLDAPサーバー
第17章 プロキシサーバー(Squid)
第18章 データベースサーバー(MariaDB、MySQL、PostgreSQL)
第19章 仮想化(Docker、LXC/LXD)
第20章 付録
まとめ
Linuxはサーバー制作から動画制作までさまざまな分野で使います。そのため何から勉強を始めればいいのかなかなかわからないと言う方はまずは本を購入し、それを使って学習するのがおすすめです。
特にやりたいことが決まっていないとという方はまずはコマンドの使い方に詳しい本を買うと良いでしょう。ディレクトリの操作や環境構築などの言語を使うにしてもLInuxコマンドは必須の分野です。まずはLInuxコマンドに慣れるところから始めてみましょう。
エンジニアとして転職を考えるあなたへ
①自分のスキルについて詳しく知る
②自分のスキルについてより知識や知見を深める
②転職活動成功のノウハウを学ぶ
以上のようなポイントを抑えることで、
あなたのスキルをより強度で豊かなものへと成長させると共に、転職活動の成功をおさめることにもつながるでしょう。
このサイトでは今回紹介した内容以外にも、たくさんの情報を記載しております。
下記の記事にも触れておくことは、あなたのスキルアップやキャリアアップの後押しになることでしょう。
Rubyを独学で習得した人にオススメのキャリアプランを3つ紹介
なぜRubyの求人は少ないの?その思い違いに至る原因を暴露
【プログラミング初心者向け】JavaScriptのオススメ講座3つ
エンジニア転職について詳しく知るために
エンジニアとしてキャリアアップをしていく方法として「LUIDA」を活用してみましょう。
「LUIDA」はゲーム感覚で気軽に転職活動ができる、これまでにない楽しさが自慢のエンジニア転職サイト。
LUIDAでは、参加登録後は企業からの指名を待つだけでOKです。
リアルな年収や業務内容が提示されますので、面接の時間や労力を節約し効率的に転職活動を行えます。
LUIDAを活用し、あなたも楽しみながらにエンジニアとしての市場価値を高めていきませんか?